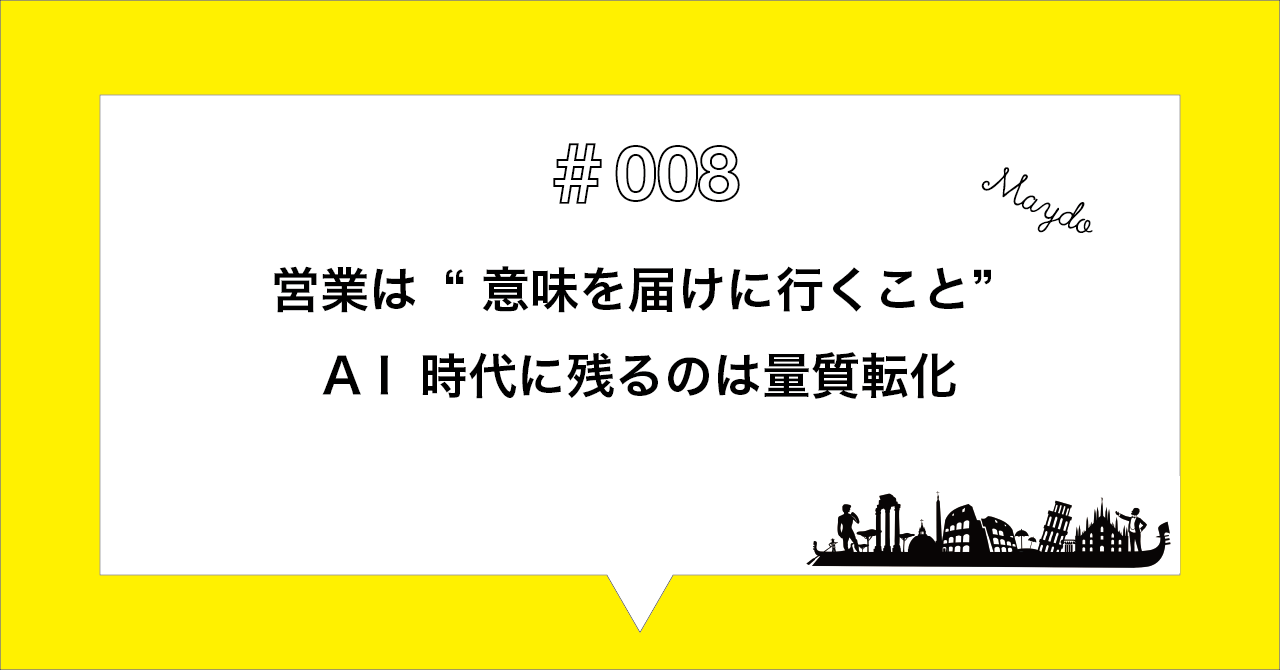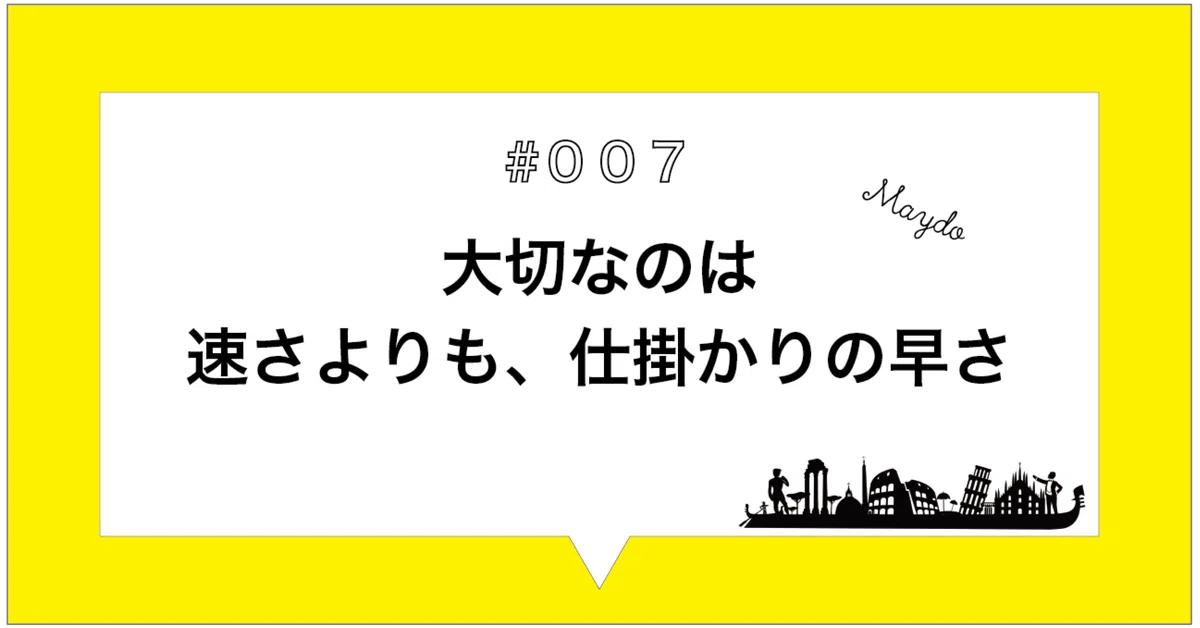今週、姫路で行われる打ち合わせに参加してきた。
豊岡から姫路へ。距離にすれば電車や車で1時間30分ほどかかりますが、この「自分から動いて会いに行く」こと自体に、今の時代だからこそ大きな意味があると感じています。
僕はこれを「営業」と呼んでいます。
でも、いわゆる“ゴリゴリの営業”ではありません。営業を「売り込み」と考えてしまうと、どうしても身構えてしまいますよね。僕が大事にしているのは、営業=自分の意味を届けに行くことです。
みなさん、記事を読みにきていただいてありがとうございます。
森下です。初めて見ていただいた方は、ぜひnoteの自己紹介もご覧ください!
https://note.com/embed/notes/n44dd574f49ba
目次
- 営業=意味を届けに行くこと
- AI時代に求められる“量質転化”
- 地方で動くからこそ見える景色
- AIではできない「意味を持って動く」こと
- 結び
営業=意味を届けに行くこと
地方で仕事をしていると、「待っていても仕事が来るんですか?」とよく聞かれます。
もちろん、待っているだけではチャンスは限られます。声をかけてもらうこともありますが、その背景には「こちらから動いている」という事実があります。
営業とは、単に商品やサービスを売り込む行為ではありません。
「自分がやっていることには、こんな意味がある」「あなたにとって役立つのは、こういう部分です」と、相手に自分の存在を届けること。そこに共感や信頼が生まれたとき、自然と仕事につながっていきます。
だから僕にとって営業は、「意味を伴った出会いのデザイン」なんです。
AI時代に求められる“量質転化”
ここで出てくるのが、量質転化という考え方です。
たくさん動く。たくさん会う。たくさん仕掛ける。その量を積み重ねた先に、質が生まれる。
でも今、多くの人は「最短距離」を好みます。AIを使えば、効率よく答えにたどり着けます。リモートを使えば、ゼロムーブで会議に参加できます。無駄を省き、合理的に動くことが正解だとされがちです。
しかし、AIは「効率の担保」には最適でも、「意味の創出&信頼の貯蓄」には限界があります。
人間だからこそできるのは、一見遠回りに思える量の積み重ね。その中で、予想もしなかった出会いや、偶然の気づき、相手からの反応が生まれるのです。
営業もまさに同じ。
最短距離で売るのではなく、動き続けることで信頼や関係性が育ち、ある瞬間に質的な転化が起こる。それが「この人に頼みたい」と思われる瞬間です。
地方で動くからこそ見える景色
豊岡に拠点を移して以来、僕はあえて「自分から動く」ことを意識しています。
地元の事業者に会いに行く。行政や観光関係者に声をかける。時には大阪や東京へも足を運ぶ。そして今回は姫路。
地方にいると、「呼ばれるのを待つ」姿勢になりがちです。都会に比べてイベントや人材の動きが少ないからこそ、受け身になってしまう。でも逆に言えば、地方で自ら動いた人には、必ず大きなリターンがあります。
僕自身も、動いたからこそ出会えた人、広がったご縁がたくさんあります。
その一つひとつが、今の仕事やブランドづくりの基盤になっています。
そしてやはり、仕事になっていっている現状があります。
AIではできない「意味を持って動く」こと
AIがどれだけ進化しても、実際に人と会い、声を交わし、関係性を築くことは、人間にしかできません。しかもその中で「意味を持って動く」ことは、単なる効率とは全く別物です。
営業=意味を届けに行くこと。
これは、AI時代にこそ残る人間らしい行為だと思います。
動きの量を重ねることで、やがて質的な変化が訪れる。
量質転化のプロセスは、一見すると地味で時間がかかるかもしれません。でも、それが地方で挑戦する僕たちの最大の強みになるのではないでしょうか。
結び
営業とは、誰かを説得することではなく、自分の意味を相手に届けに行くこと。
AIが効率を担保してくれる時代だからこそ、僕たち人間に残されているのは「量を重ね、質を転化させる」営みです。
豊岡から世界へ。地方から動くという小さな一歩が、未来の大きな転機になる。
そう信じて、今日も僕は“営業”に出かけます。