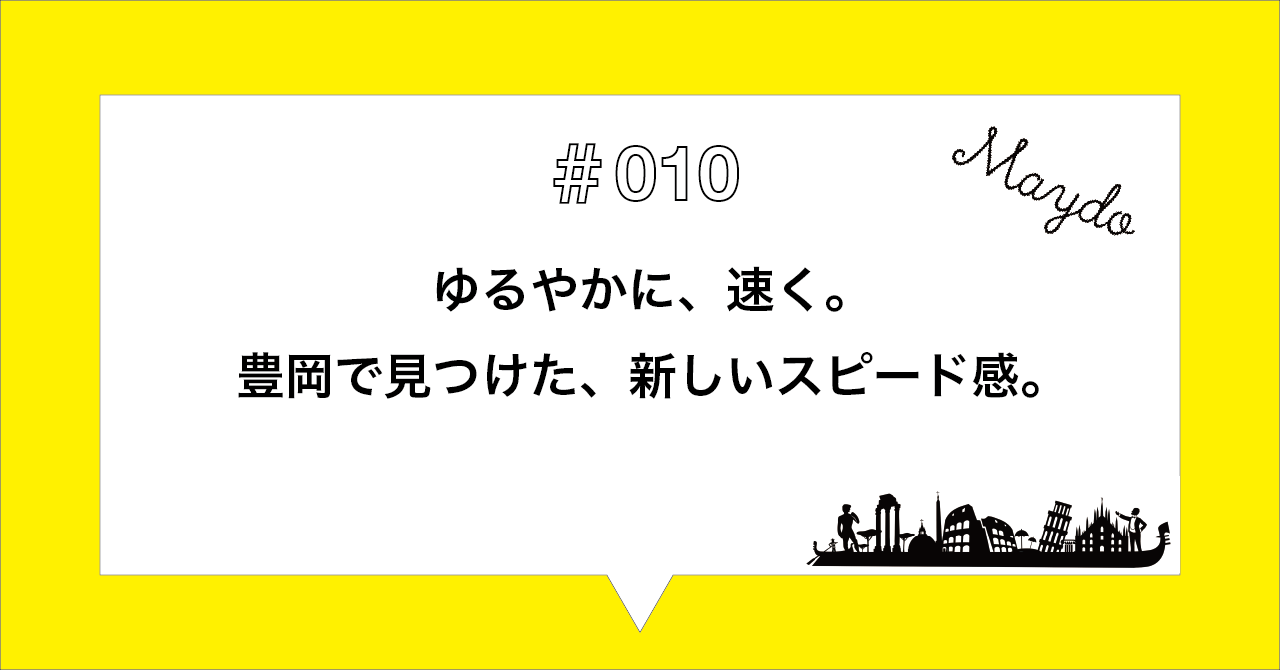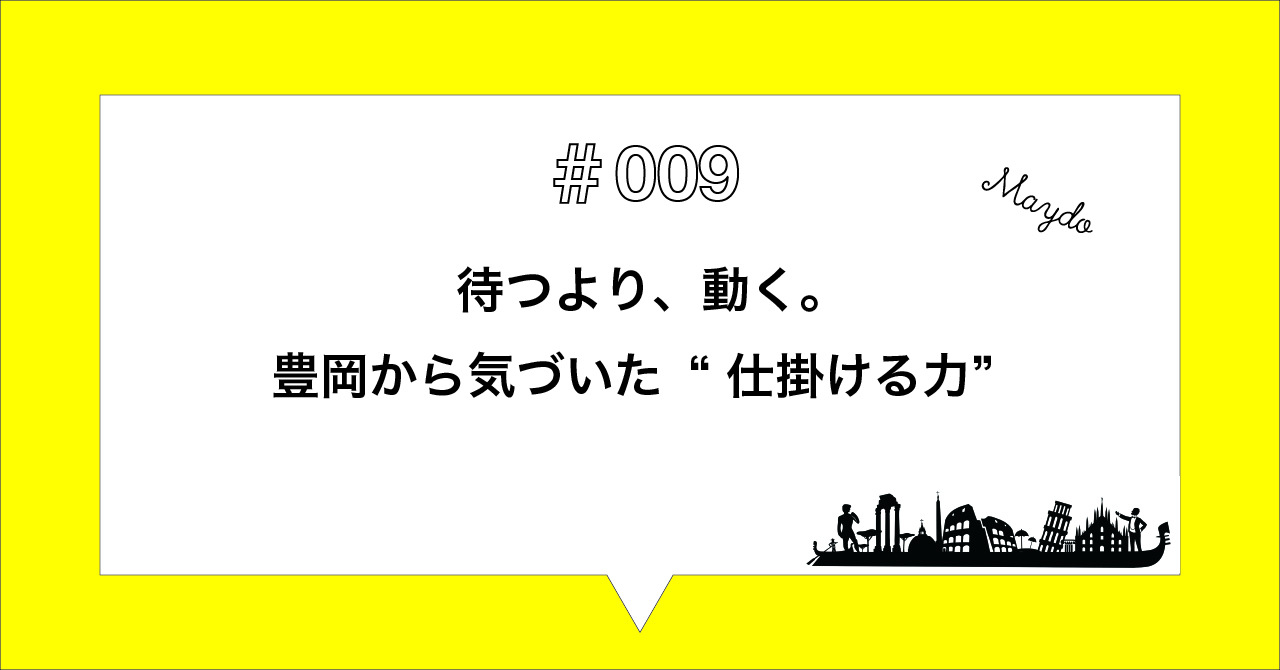豊岡に来て、気づけばもう5年が経ちました。
この街に来る前は、地方に住むということに、どこか“スローライフ”的なイメージを持っていました。
「ゆっくり暮らす」「急がずに生きる」
そんな言葉が、地方の象徴のように感じていたんです。
でも、実際に暮らしてみると、少し違いました。
確かに、都会のような“ノイズの多い速さ”はない。
だけどその代わりに、「意味のある速さ」が生まれていく感覚があったんです。
みなさん、こんにちは。ブランディングカンパニーMaydoの森下です。僕の記事を初めて見ていただいた方は、ぜひ自己紹介ページもご覧になってください!
https://note.com/embed/notes/n44dd574f49ba
目次
- スピードを落としたら、むしろ速くなった。
- コミュニティよりも、関係性の深さを。
- 「仕掛かりの早さ」が、地方のチャンスを広げる。
- 豊岡で磨かれていく「速さの感性」
- おわりに
スピードを落としたら、むしろ速くなった。
豊岡に移住して最初の頃、仕事のスピードをどう保つか不安でした。
打ち合わせの数も減り、刺激的な出会いも都会に比べれば少ない。
「このままでは取り残されてしまうんじゃないか」
そんな焦りもあったのを覚えています。
でも、時間が経つにつれて、考え方が変わっていきました。
「動く」こと自体に追われていた都会のスピードよりも、
“なぜ動くのか”を考える時間がある今のほうが、
結果的に“仕掛ける”スピードが上がっている。
本当に意味のあるものに集中できるようになったことで、
準備も、行動も、成果も、むしろ加速していったんです。
コミュニティよりも、関係性の深さを。
豊岡に来て感じたのは、
「広くつながる」よりも「深くつながる」ことの大切さ。
イベントやプロジェクトを重ねるうちに、
“地域のつながり”という言葉の本質が少しずつ見えてきました。
それは、“誰かに会うために動く”というより、
“意味のある出会いに向けて動く”という感覚。
一見、ゆるやかに見えるけれど、
実はすごく速い。
目的が明確だから、余計な迷いがない。
先回りして、準備しておくと、すごく喜ばれる。
「仕掛かりの早さ」が、地方のチャンスを広げる。
地方で仕事をしていると、
「スピード感がない」と言われることがあります。
でも、本当は“速く動く”ことよりも、
“早く仕掛かる”ことの方がずっと大切なんです。
準備を早く整えて、
必要なタイミングで打てるようにしておく。
この“仕掛かりの早さ”があるかどうかで、
結果の出方が大きく変わる。
地方であっても、いや、地方だからこそ、
この「早さの質」を意識することが求められる時代だと思います。
よく言われる「ぶん投げ」的なことに疲弊する方も多いと聞きます。
そんな時は、指示を待つのではなく、幾つも新しいパターンを準備しておくとうまく進みます。徹底的にギブをしていくというスタイルです。
豊岡で磨かれていく「速さの感性」
都会のスピードに慣れていると、
最短距離で結果を求める癖がついてしまう。
でも、地方にいると、
遠回りの中にこそ意味があることに気づく。
地元の人との信頼関係を築く時間、
ゆっくり発酵していくようなプロジェクトの流れ、
一見“遅い”ようでいて、
実は深い速度で世界が動いている。
「ゆるやかに、速く。」
この5年で自分の中に根づいた言葉です。
焦らず、止まらず、意味を持って動く。
そのバランスを掴めた時、
地方からでも、どこまでも届くスピードが生まれると思っています。
おわりに
「地方に行くと、スピードが落ちる」
そんな先入観を持っていた過去の自分に、今ならこう言いたい。
“速さ”は、場所ではなく「意識」から生まれる。
焦らず、意味をもって、仕掛かる。
それが、地方で挑戦を続ける僕のスタイルです。